倒立する塔の少女~別れの再生産の視点から~
1.端書き
劇場版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』の上映が始まった。
以前私はTV版をオタクの勧めで鑑賞し、ちょっとした評論めいたもの(愛城華恋とは誰だったのか ―密室を覗くということ、あるいは落下する読者― - Krankenhaus)を書いたことがあって、その際もうこの作品については何も書かねえといった趣旨の発言をしたのだが、性懲りもなくこうしてオタク顔でキーボードを叩いている。
列車が必ず次の駅に向かうように、舞台少女が次の舞台に向かったように、私もケリをつけなければならないと思ったから――というのはさすがに格好つけすぎだが、情熱の赴くままにやれと西条クロディーヌも言っていたことだし、覚書程度に記すことにする。
なお、本稿に引用する画像は主にまたちょうどいいタイミングで全話配信を始めたYouTubeの公式チャンネル(スタァライトチャンネル - YouTube)から拝借している。また、引用する台詞はすべて稿者によって文字起こしされている。劇場版については参照性がないから多少の異同があるかもしれない。一応3回は観たので大意には影響はないはずである。
2.これはオーディションにあらず
TV版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』はトップスタァの座を賭けたオーディションが物語の骨格となっていた。では劇場版はどうか。
TV版のオーディションからちょうど1年、突如始まった「ワイルドスクリーンバロック」に、花柳香子は思う――またオーディションが始まった、と。
しかしこれは大場なな、そしてのちにキリンによって否定される。「これはオーディションにあらず」。
オーディションとは、役者を登用するための選抜方法の一種である。その構造上、一般に配役の数だけしか競争を勝ち抜けない。トップスタァは舞台にひとり、だからこそふたりで「運命の舞台」を目指す華恋とひかりはTV版で苦悩し、その末にふたりでスタァライトをすることに成功した。
劇場版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』はオーディションではない。つまり、そこに勝者がいないことは、序盤においてあらかじめ明示される。
3.トマトとは何か
劇場版においてトマトは重要なアイテムとして登場する。これについては先達が散々考証を重ねているだろうし、実際いくつかを拝読した。だから今さら鬼の首をとったようにこれを深堀りしても仕方がないので、本論に必要な範囲で一応触れておく。
結論から言って、トマトが「舞台少女に新たな血を吹き込み、次の舞台へ向かわせるもの」として描かれていることは間違いない。
囚われ変わらないものは、やがて朽ちて死んでいく。立ち上がれ。古い肉体を壊し、新たな血を吹き込んで(中略)たどり着いた頂に背を向けて。今こそ塔を降りる時。*2
第101回聖翔祭決起集会で読まれた『スタァライト』第1稿のこの台詞は、舞台少女のこれからを強く示唆する。というよりそもそも同じ舞台を再解釈し演じるという学園のシステム自体が、この代謝を表している。 『ロンド・ロンド・ロンド』でキリンが舞台少女の本質と『スタァライト』を同一視したのはこのためであり、大場ななが見た「舞台少女の死」とは、つまり舞台少女としての停滞のことを指すのである。
舞台が終われば、次の舞台へ――舞台少女の「野生(wild)」は彼女たちを駆り立てる。
みんな、新しい舞台、立つべき舞台を求めて、すぐに飢えて、乾いて――。*3
赤くみずみずしいトマトが連想させるのは血である。渇きを潤し、血肉となって舞台少女を蘇らせるものとしてトマトは機能している。また、赤はどうしようもなく運命を想起させる点にも留意すべきだ。*4
これに当初当惑の色を見せたのが星見純那だ。彼女は飢えや渇きから目を背け、何にケリをつけるべきなのかを戸惑う。だからこそ大場ななとの「介錯」シーンで大場ななは星見純那を「いずれ熟れて落ちる果実」と表現し、切られた軍帽からは血が噴き出すのである。
愛城華恋はずっと神楽ひかりとの「運命の舞台」を夢見て舞台に立ってきた。そしてそれは第100回聖翔祭において達成される。目的を達成した華恋は熟れ、内圧に耐えかね破裂してしまった。「死んでる」のは、生物としての愛城華恋ではなく、舞台少女愛城華恋だった。
新しい、次の舞台へ向かうことが、本作のテーマであり、トマトはその装置としての役割を担っている。
舞台は、私たちの心臓。歌は鼓動、情熱は血。私たちは、舞台に生かされている。傷ついても倒れても、舞台が私たちを蘇らせる。舞台少女は何度でも、生まれ変わることができる。*5
4.倒立する塔について

戯曲『スタァライト』の塔や、ひとりしか勝ち上がれないオーディションの象徴(頂点はひとつなので)としてTV版から長くその役目を果たしてきた東京タワーは、本作において倒立する。映画の最後、華恋をひかりが貫くと同時に、東京タワーは真っ二つに割れ、その先端はクソでかいポジションゼロに突き刺さる。この意味についてすこし考える。
劇場版において勝者はいないと先述したが、厳密には正しくなく、実際には少女たちはそれぞれの舞台に立ち、戦い、勝敗を決し、各々のこれまでにケリをつけていく。特徴的なのはそれらの勝敗がこれまでを通じて描かれた関係と逆転することである。
石動双葉は花柳香子を「待たせる」ようになり、大場ななはそれまで星を見上げるばかりだった星見純那を「眩しい」と仰ぎ、天堂真矢は西条クロディーヌに魅せられ、そして神楽ひかりは愛城華恋に再び手紙を送る。露崎まひるは少し特殊だが、TV版に引き続き今度は神楽ひかりへの私怨を清算し、自身の道を進むことを決意する。
この関係の逆転と倒立する塔のモチーフの対応は、TV版でもすでに見られ、窮地にてきらめきを取り戻したひかりが大場ななを一転攻めるシーンでは、ひかりの攻勢に呼応するようにタワーの先端が落下してくる。
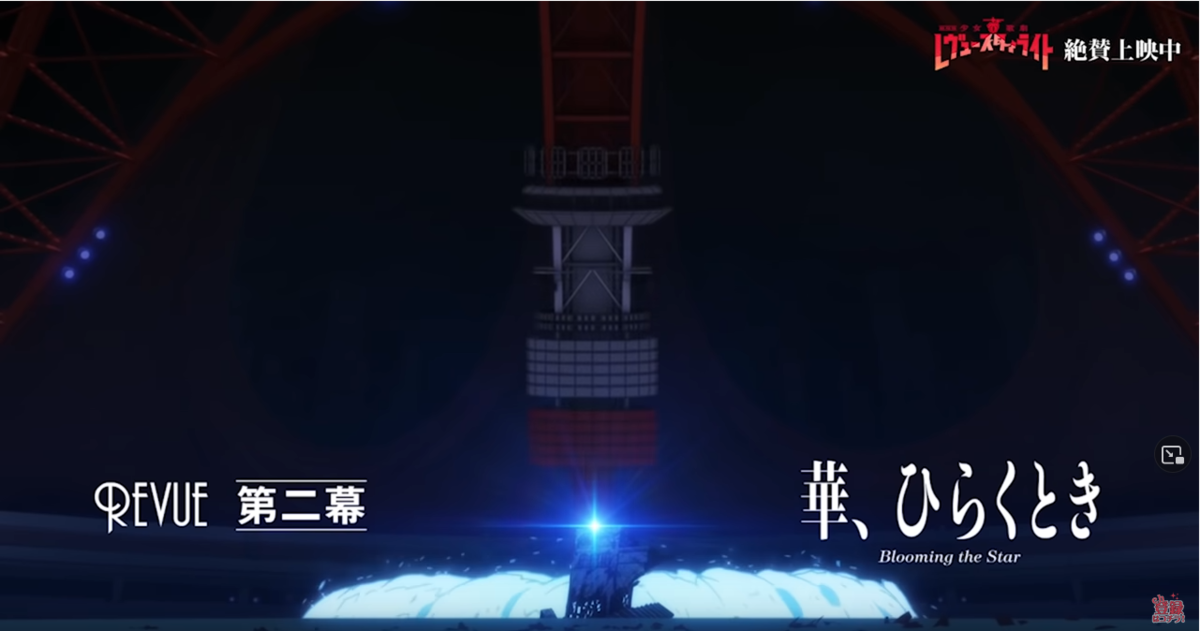
このように倒立する東京タワーは関係の逆転を表し、またそれはこれまで絶対と思われた頂の唯一性が毀損されることを示している。塔が倒れ、失われたからこそ、少女たちは塔から降り、今度はどんな塔にも登り始めることができる。塔をあえて破壊してみせ、また「再生産」してみせることによって、舞台少女たちは初めて自由になったのである。
5.戯曲『スタァライト』は別れの舞台
わたしたちは、一緒にいられない。この舞台は、別れのための舞台。*6
戯曲『スタァライト』は別れの物語である。この悲劇を、別れの続きを描くことで克服しようとしたのがTV版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』であり、第100回公演だった。『スタァライト』が別れの舞台である以上、いくら再解釈しようとその筋書きは別れからは逃れられない。では劇場版において別れはどのように描かれているか。
戯曲『スタァライト』はフローラとクレールによる悲劇である。TV版においてこの役を担ったのは言うまでもなく華恋とひかりだ。では塔が「再生産」され、乱立する世界で、その役を担うのは誰か。それはもちろん愛城華恋と神楽ひかり、あるいは露崎まひるであり、石動双葉と花柳香子であり、大場ななと星見純那であり、天堂真矢と西条クロディーヌである。本作は舞台少女たちの決別を描いた物語であり、やはり別れの舞台なのだ。
示唆的なのは大場ななと星見純那によるワイルドスクリーンバロック④の中の一幕、ふたりが別々の舞台へ歩みを進めるシーンである。ふたりの道はともに伸びたポジションゼロ上にあり、ここで我々は改めてこれがオーディションではないことを思い出す。これはTV版12話においてひかりと華恋がポジションゼロを分かつようにして舞台に引き離されるのと実に対照的である。
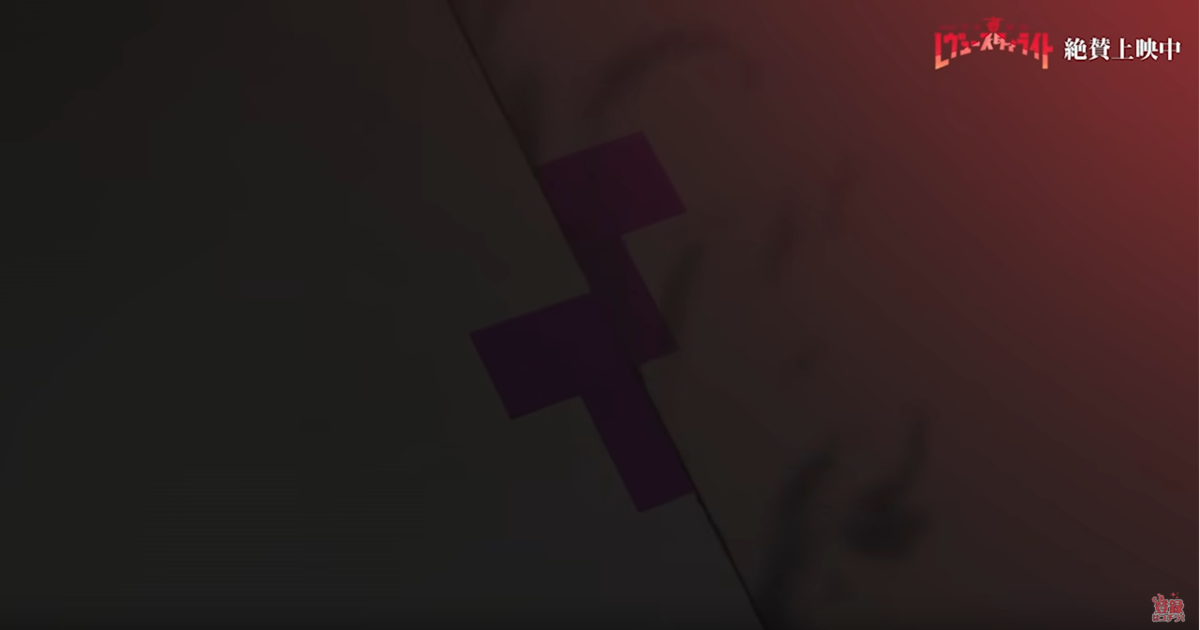
自由を手にした舞台少女が、これまでと決別して今度はそれぞれの頂に向かって歩き出す――劇場版の別れは第99回、第100回より前向きなものとして再解釈されている。また決別は少女間の関係だけではない。華恋は舞台少女として生まれ変わるためにこれまでの過去(運命の舞台に囚われてきた自分)と照明の熱で焼き払う。運命の舞台の実現を目指したTV版はあれはあれで美しいが、とどのつまり他人に依存した情熱でしかなく、舞台少女であり続けるためにそれは許されなかった。そして運命の舞台から解放された華恋は最後に言うのだ。「ひかりに負けたくない」。
6.結語、あるいはチラシの裏
たらたらと続いた感想文もここでおしまいである。劇場版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』、とてもおもしろかった。でけえ音で音楽を聴くのはやっぱり良い。
私もこれを書いて、ひとつケリをつけたことにする。舞台少女たちが「現在、今この時」もそれぞれの舞台で塔を登っているように、私も次に進まなければならない。いつまでもクネクネしている場合ではない。
今こそ塔を降りる時。
私と犬の話
私の犬がもう永くないというので、ひさしぶりに帰省することにした。
そう、私の犬だ。私が実家を出てからもうしばらく経つから、実際彼女の世話をしているのは私の父と母だけれど、それでもあえて誰の犬かと言われれば、私の犬ということになる。
彼女は血統書のつくような、立派な犬ではない(しかし彼女は立派に犬をやっている、すくなくとも私よりはよっぽど犬だ)。保健所にもうすぐ入れられるところを、私がねだってもらってきたのだった。
本当は雄がほしかった。というのも雌の避妊手術にはお金がかかるから。私もそのつもりで、何日も費やして、そして胸躍らせながら、男性名を考え抜いた。
けれど譲渡会の当日に、雄はいなかった。ちょうどいま最後の一匹がもらわれていったところですと、職員らしき人が言った。落胆する私の足元に無邪気にまとわりついていたのが、彼女だった。今でも彼女は男性名で呼ばれている。
彼女はよく人に懐いた。知らない人にもすぐに腹を見せた。私たちも、番犬を雇いたいわけではなかったから、それでよかった。
役割とは居場所のことだ。私たちは何かを担うことでここに居てもいいという許しを乞うている。赤ちゃんは泣くのが仕事だし、犬は飼い主に忠実でなければならない。
その点彼女はお世辞にも優秀とは言えなかった。人によく懐くくせに、人の言うことをあまり聞かなかった。彼女はいつだって望めるだけの自由を、それがたとえほんのすこしだったとしても謳歌していた。
ひさしぶりにみた彼女は、痛々しいほどに老いていた。両目はうっすら白濁して、ほとんど骨と皮だけにみえるからだは不自然に折り畳まれようやく自力で立ち上がれるような状態だった。まだぎりぎり視力は失っていないのか、私を一瞥すると、時間をかけて立ち上がった。頭をなでると彼女は身を震わせた。どうやら目は見えていても遠近感はうまく働いていないらしい。驚かせたことを謝ったが、反応はなかった。
犬は私たちよりはやく死ぬ。私がうっかり明日死んでしまわないかぎりは、そういうふうにできている。
犬は人語を話さないし、私の言葉が通じているかも、結構疑わしい(すくなくとも見かけ上は通じているように彼女は振る舞うけど)。
そういえば一度だけ、彼女は家を逃げ出したことがある。新しく買った首輪がゆるかったせいだ。赤い新品の首輪を残して彼女は走っていってしまった。私はその時もう彼女には会えないのだと思った。そう思うとかなしくて、たしか泣いてしまった。もう会えないことよりも、共通の言語を持たない私たちに、いつの間にか確執や軋轢のたぐいが生じていたのかもしれないという可能性がかなしかった。不満があっても彼女にはそれを伝える手段がほとんどない。それがかなしかった。
ところが彼女はその日のうちに帰ってきた。あちこち探しまわって帰ってきた私を、家の前で待っていた。なぜか体はぐしょぐしょに濡れていた。
犬にも帰巣本能みたいなものがあるのかを私は知らないし、給餌と一定の安全が保証された場所以上の意味を彼女がそこに見出したのかはわからない。でも、彼女はそこを選んだのだ。それは言葉を持たない彼女がみせた、明らかな意思だった。私はそれがうれしかった。
犬は頭がわるいから、君はうちに来てしあわせだった? となでながら聞いてみても、なでられていることにご満悦のようで、ちいさく鼻を鳴らすだけだ。難しいことなんて何も考えていないようにみえるが、案外彼女が言葉を得たら、数々の不平不満が飛び出すかもしれない。
願わくはそれが、名付けに関するものでないことを、私は祈っている。
ミネット・ウォルターズ「養鶏場の殺人」考――誰がエルシー・カメロンを殺したか?
互に拒んではいけない。(中略)そうでないと、サタンがあなたがたを誘惑するかも知れない。(コリントの信徒への第一の手紙7:5)
ミネット・ウォルターズ「養鶏場の殺人」は1924年、イングランド南東部で実際に起きた殺人事件を題材にした中編小説である。おまけに最後には本件に関する著者の(それが憶測に近いものだとしても)推理までついてくる。爽快な解決や張り巡らされた謀略があるわけではないが、現代英国ミステリの女王とも目される彼女が、この事件をどうみたのか、それが知れるだけで喜ぶファンはいるだろうと思う。
しかしながら、あえて結論から言わせてもらえれば、その「著者のノート」こそ、本作においては蛇足だったのではないか。いや、厳密にいえば本筋のテクストとの食い合わせがかなり悪い気がしている。20世紀のイングランドで起きた事実がどうだったかはともかくとして、本作というテクストに対応する読みとしては誤読してないか? というのが本稿の起点だった。
したがって、本稿では、本作を「事実をもとにした小説-事実に対する著者の私見」という関係ではなく、「一個のテクスト-それに対する読み」という視座から鑑賞してみたい。
1.物語の構造と展開
エルシー・カメロンは神経質な女性だ。行き遅れかけていて、何事も何かのせいにする癖があり、落ち込みやすく、感情の起伏が激しい、「おとぎ話のお姫様」を夢見る小柄で不器量な女性だ。エルシーは神ではない「誰かに愛されたかった」。
エルシーはひとりの青年に恋をする。4歳年下の、戦争帰りの技師ノーマン・ソーン。交際を始め、順調にみえたふたりだったが、ノーマンの失業、養鶏業の不振から、徐々に不和が生じるようになる……。
物語はエルシーが初めてノーマンに声をかけるところから始まるのだが、そこではこうある。
教会で出会った男性がその四年後に、ブラックネス・ロードという場所で自分を切り刻むなどと、だれに予想できるだろう。
本作を最後まで読み、改めて立ち返ると、じつに意地の悪い仕掛けであることがわかる。ノーマンはエルシーを「切り刻」んだ。しかしここでは「殺した」などとは一言も書かれていないのだ。倒叙に見せかけ、我々はある種の先入観に誘導されながらノーマンをまなざすことになる。同じく収録されている「火口箱」でもそうだったが、こういう偏見が事件をまなざす視野をいかに狭窄させるか、みたいなひねた作為を感じないでもない。最終的に結末へ疑義を提示することが目的ならなおさら。
物語は三人称視点で語られるのとはべつに、ふたりの文通パートが挿入されるかたちで構成され、ふたりの愛の温度差が生々しく強調されている。
ふたりの温度差は、次のように残酷に描写される。
エルシーは眼鏡をとると、見えていない目でノーマンを見つめた。
(中略)「愛してちょうだい、ペット、お願い。あなたなしでは生きられないの。わたし、とても……寂しいの」
エルシーはノーマンが「見えていない」。盲目的な恋に身をやつしているのだ。神以外の誰かに愛されたかったエルシーは、新たな神を発見する。神を信仰するのに、その姿かたちはもはや意味をなさない。しかしノーマンはこれを無情にも拒絶する。
「彼女は目がよく見えなかったんです……でも、眼鏡をかけていないほうが見た目がいいと、自分では思っていたんです」
「で、そうだったのか?」
「いいえ」
残酷なまでに対比されたこれらの描写は、陰鬱な本作の雰囲気にさらに影を落とす。(とてもつらい!)
エルシーの癇癪に振り回され、養鶏業も軌道に乗らず、ノーマンは徐々に追い詰められていく。そんなときエルシーが行方不明となり、その死体がばらばらに切断された状態で養鶏場から見つかるのだ。上述の通り死体を切り刻んだのはノーマンである。
では、エルシーは他殺か、自殺か?
誰がエルシー・カメロンを殺したか?
物語は、無視するには大きすぎるしこりを残したまま、幕を閉じる。
2.ノーマン・ソーンと信仰
ノーマン・ソーンはとても信仰に篤い青年として描かれている。「教会の奉仕活動にはすべて参加して」いて、自身の養鶏場にジョン・ウェスリーにあやかってウェスリー養鶏場と名前を付けている。
加えてノーマンは野心家だ。少なくとも戦争で「ヒーロー」になれなかったことを悔やみ、恋人の勧めがあったとはいえ養鶏業で成り上がろうと一念発起するくらいには。
すこし話が変わるが、本作において「鶏」と「エルシー・カメロン」は緊密な対応関係にある。ノーマンが鶏を屠殺するシーンは否応にもエルシーのばらばら死体に連結するし、後半の警部は船越英一郎ばりにエルシーを鶏になぞらえて説教する。
鶏を殺すのにもいちいち胸を痛めるようなノーマンが、なぜ自らの恋人に手をかけた(かもしれない)のかは、彼の信仰心を追うことですこし見通しがよくなる。
さて、あなたがたが書いてよこした事について答えると、男子は婦人にふれないほうがよい。(コリントの信徒への第一の手紙7:1)
ご存じの通り、キリスト教は婚前交渉を推奨していない。ひとはまず独身であるべきで、それがかなわないならば結婚するべきである、婚前交渉などは姦淫にあたるとして、カトリック教会などでは厳しく取り扱われる。
ノーマンは若者並みの性欲を持て余していた。実際ノーマンは何度かエルシーに迫っている。避妊具の着用を是としているから、避妊を罪とする極端な思想は持っていないのかもしれない。それでもノーマンはエルシーの意に反した行動にはおよばなかったし、教会の教えは歯止めとして十分機能していた。
ノーマンが初めて教会の教えに疑問を抱いたのは養鶏業が上手くいかず、金銭的にも苦境に立った時だった。
神はみずから助くる者を助く、とノーマンは教えられてきた。そして、勤勉はそれ自体が報いである、と。しかしそれでも、ノーマンの胸から不安が消えることはなかった。
そして、追い詰められたノーマンは、ついにベシー・コルディコットと不義を働くようになる。うら若く、エルシーと違い何も要求しない彼女はノーマンにとって好ましく映ったのだろう、婚約を済ませた恋人を差し置いてふたりはセックスをするようになる。そこには若者の意気を敬虔な信仰で自制していた誠実な青年はもういない。
彼の信仰はこの時点で堕しているとするのが妥当である。事実、警部補に彼が「聖書にかけ」て真実だと誓った、エルシーとは「十一月の最後の日以来会って」いないという供述は、虚偽だった。
3.「著者のノート」の是非について
ここで本題に戻ろう。誰がエルシー・カメロンを殺したか? である。
ノーマンの信仰がすでに堕しているとするならば、物語の最後、絞首刑を言い渡され、一貫して嫌疑を否定するも上訴を却下され、刑執行を迎えた彼が最期に父親にあてた手紙はどうなるだろう。
一瞬のことで、それですべてが終わります。いや、終わりではなく、神のもとへの第一歩です。ぼくはそこで父さんを待ちます。亡くなった人たちがぼくを待っているように。ぼくは無実です。愛をこめて……
これについて、著者は「著者のノート」において次のように言及する。
わたしが興味を引かれるのは、ノーマン・ソーンが一貫して、エルシー・カメロンの殺害を否定していることだ。それは絞首台を前にしても変わらなかった。最後まで彼は、自分はエルシーが梁からぶらさがっているのを見つけたのだと言いつづけた。だからといって彼が無実だということにはならないが、もし彼が有罪ならば、神を信じる若者にとって、これは危険な賭けである。ノーマンは、天国行きを望むならば罪人は自分の犯した罪を悔い改めなければならないことを知っていた。
加えて著者は未必の殺意も否定し、供述のある一点をもってその信憑性を弁護する。実際のところ、事実は著者が作中で示したようなものなのかもしれない。しかし、繰り返すが、本作を一個のテクストと考えると、ノーマン・ソーンの信仰はベシーとのセックスによってすでに堕落しているのである。とすれば、「聖書にかけて」真実と誓ったあの供述が嘘であったのと同様に、「ぼくは無実です」という言葉はまったくもって逆の意味になりかねない。両者の言い分を拮抗させ、問題提起を趣旨にするには、ノーマン・ソーンという人物はあまりに脆弱すぎた。その点、著者はテクストを誤読していると言えるだろう。
問:誰がエルシー・カメロンを殺したか?
答:ノーマン・ソーン
追記:本稿は、エルシー・カメロンを誰が殺したのかを、一個のテクストとして読んでみようという動機で書かれているが、本作が過去の事実に立脚した物語である以上、一定の配慮が必要であるように思われる。つまり、本稿は、実在の人物の名誉を毀損することを企図しないことを、改めてここに明言しておく。
わたしのすきな音楽について(邦楽編)
特に暇と言える程暇ではないはずである。すこしのやらなければならない事項と、大量のやったほうがよい事項があって、少なくともこんな文章を綴っている場合ではないはずだが、なんとなく気乗りがする方向に流されて、こうしてこれを書いている。
わたしは音楽がすきだ。おそらく。
私より音楽に詳しくて、音楽を愛している人もたくさんいる(というか、インターネット上でじっさいに観測している、それも大勢!)。しかし、それでわたしが音楽をすきではないということにはならないはずであるし、少なくともわたしはわたしのすきなものを公言する自由がある。一体どこに需要があるのかわからないが、まあなくたって手慰みくらいにはなると思う。何度も言うが暇ではないはずなのだが。
というわけでわたしのすきな音楽をざっと以下に並べてみる。今回に関しては邦楽に限定している。洋楽も交えるとそれはもう手慰みでは済まなくなってしまうだろうし、わたしの仕事ではないような気がしたから。もしかしたらべつの機会にやるかもしれない。
基本的にはアーティスト名での紹介とするつもりだが、特におすすめの盤がある場合はそれも付記する。あと、今更「良いものは売れる」を体現しているようなアーティスト(スピッツとか)を紹介しても仕方ないと思うので、比較的中堅以下のアーティストを中心に紹介する。
それでは。
1.andymori
いきなり有名どころで申し訳ない。でも良い。やっぱり良いものは良い。中学の時は小山田壮平がすきすぎて早稲田に行きたかった。不祥事なんか才能の前では些事なんだなと思った。変拍子! キモぺジオ! が合言葉だった当時の音楽シーンのなかでは異端だったくせに走っていたのはちゃんと王道だった。かっこいい。
2.bronbaba
toe はきれいすぎるよなあという人は聴くといいかもしれん。まああんまり書くことないけどすき。
3.colormal
宅録ですげー良い曲つくる人がいるなと思っていたらむかし一ノ瀬志希の曲できもいアレンジ(褒め言葉)していたのをインターネットでみたことがあった。本人がすきだと公言しているように GRAPEVINE に近い感覚で音楽をやっている感じがする。ライブに行きたい。
4.the cabs
世界でいちばんすき。まじでキャブスだけで 20000 字くらい書ける。ここ最近作詞作曲担当のフロントマン feat.ゆかいな仲間たちみたいなバンドが増えてきたけど、かれらは誰が欠けてもだめだった。首藤義勝はいまテレビで鉛筆を舐めているらしい。無念でならない。
高橋國光は最近精力的に活動していてすごい嬉しい。Sound Cloudにあがる別名義の音源はどれもチープな打ち込みの粗が目立ってかなしかったが、死なずに音楽を続けてくれているだけでまあひとまずは満足だろと思っていたらこのあいだどこぞの地下アイドルに提供した曲が死ぬほどよかった。
ちなみに大学時代、寄ってきた女にすすめたら「たのしそうな曲だね」と返ってきてフった経緯があり、以来人に勧めるのはやめている。
おそらく不動のオールタイムベストだ。
5.Gateballers
さいきん知った。「スーフィー」って曲がすきなんだけど、どうやらジャラール・ウッディーン・ルーミーからきているらしくておったまげた。べつに音楽と直接は関係なくても、あー知性がバンドやっとるなとなれるので良い。
6.kik vivi lily
あんまり詳細がでてこなくてわからないけど、多分ファンク、ヒップホップ、ブラックミュージックあたりがすきなんだろうなって感じ。黒人のやくしまるえつこと形容するとヘイトになるのかな。
7.King Gnu
紅白出場おめでとうございます。このバンドが売れるなら日本の音楽シーンもまだ捨てたもんじゃねえなと思わせてくれたバンド。東京藝大はやっぱりすげえな。
ていうか幼馴染で東京藝大へ進学、しかも片方は中退ってなんだよ、小説か? 調べれば調べるほど実家が太くてむかつくが、インタビューでぽんぽん海外アーティストの名前が飛び交うし、ドラムはブラックミュージックのそれだし、ルーツもかなりしっかりしていて聴いててストレスがない。良い。
8.Lamp in terren
去年出したアルバムから一気に良くなった。元々ボーカルが The 1975 すきを公言していたから、ようやく技術がやりたいことに追いついたのかもしれない。関西にライブに来るとだいたい行くんだけど、あれだけの音楽ができて箱が埋まらないのなんでなんだろうな。米津玄師とかバンプ藤原とも交流があるみたいだし、そのうち売れそう。歌が上手い。
9.LIL SOFT TENNIS
これも比較的さいきん知った。「Skrr Skrr to Babylone」が白眉。
10.Mega Shinnosuke
若い才能こえ~。
11.Mom
前は iPhone で作曲してたって聞いたけどいまはどうなんだろう。新譜とてもよかった。さいきんの宅録マンのなかではいちばんすきかも。
12.No Buses
YouTube でみると海外のコメントが多い。小難しいこと考えないでこれでいいんだよなっていうひとつの解答をみた気持ち。一発売れるみたいなビジョンは見えないし、本人たちも気にしてなさそう。じゃないとあんな MV はつくらんだろ。
13.nuito
解凍ライブに立ち会えたことは一生イキっていきたいと思っている。国内インストだと断トツですきです。もうバンドには興味をなくしてしまったんだろうか。このバンドを聴くようになってわたしの足元の機材はだいたい 1.5 倍くらいに増えた。
音圧はもちろんなんだけど、シームレスかつ大胆に場面を切り替える構成が上手すぎる。ゲーム音楽って転調多いしそのへんを意識しているからなんだろうか。ライブにパフォーマンスとして本当の意味で価値が付与されていると感じたのは生涯でこのバンドだけかもしれない。
14.Nulbarich
Suchmos 2 とか勝手に思っててすまんかった。めちゃ良い。
Rabbit Hole だけでいいから聴くといい。むしろそれだけでいい(そんなことはない)。
16.Tempalay
なんか韓国のアイドルに紹介された過去があるらしい。やっぱ国費で育ったアイドルは違うな。良い耳持ってる。
はじめて聴いたときの感想はこんなん Unknown mortal orchestra やんけ! だった。サイケポップ、もっと流行らないかなあ……。
17.YUUKI MIYAKE
元々はボカロピー。アメリカとかのほうが売れそう。あんまり書くこと思いつかないけど今回紹介する中でも上位に来るくらいすき。
18.雨のパレード
和製 The 1975 と言われている。そうでもなくないか? と思っているがまあ意識しているのは確かだろうし日本だと他にいないタイプだと思う。MV の画質が良い(ように感じる)。
ざっと以上である。多分、というか絶対に挙げ忘れている何かがある気がするが、まあ元々需要があるかも謎なので特に気にしないようにしておく。
愛城華恋とは誰だったのか ―密室を覗くということ、あるいは落下する読者―
およそ一か月ほど前、高校来の友人であるとあるオタクに、あるアニメを勧められた。
それが『少女☆歌劇レヴュースタァライト』だった。

この『少女☆歌劇レヴュースタァライト』、監督を務めるのは『美少女戦士セーラームーン』や『少女革命ウテナ』の監督で知られるかの幾原邦彦氏の直弟子である古川知宏氏だ。
ぶっちゃけウテナも『ユリ熊嵐』も未履修の、有り体に言えばあのあたりの作品群をなんとなく敬遠してきたぼくはこのアニメを勧められたときふーん、という具合だったのだが、この愛すべき友人はぼくとまったく趣味が合わないくせにぼくの趣味を完全に掌握しているところがあって、その点やたらと信頼できる。つまるところ観てみたらおもしろかった。
つまりこの評論(のようなもの)は、その彼にただ、勧めてもらったアニメおもしろかったよ、とそう伝えることを動機に書かれている。しかしいかに私信といえど、一応評論を自負する以上は、広い読者を意識しながら論を進めていきたいとは思っている。
また、ぼくはアニメ版『少女☆歌劇レヴュースタァライト』しか観ていない。調べたところ本作品はミュージカルや漫画など、いわゆるメディアミックス作品として世出している。後述する論点のいくつかは、あるいは他メディア作品を総合すると、まるで見当違いなものになるかもしれない。しかしまあ前述のとおり、本論の執筆動機はあくまで「勧められたアニメの感想文」なのであることだし、アニメを独立した一作品と捉えることで見えるものもあるであろうから、その点は了承いただきたい。
では前置きもこのあたりに、本論に入りたいと思う。
なお、執筆にあたってちょうどいいタイミングでYouTubeの公式チャンネル(スタァライトチャンネル - YouTube)において期間限定で全話配信が開始されたため、本論に添付するキャプチャはすべてその動画からとっている。したがって右上に広告が掲載されているが、その点重ねて了承いただきたい。台詞引用はすべてぼくが視聴しながら文字起こししたものである。
ちなみにぼくの好きなキャラクターは星見純那ちゃんである。
問題意識の共有
『少女☆歌劇レヴュースタァライト』は国内有数の演劇学校、聖翔音楽学園を舞台に、それぞれの舞台少女たちが、「最も強いきらめきを見せた」者には「トップスタァ」への道が開けるという「オーディション」に参加するなかで舞台少女としてのあり方を見つけていく、という、おおざっぱに説明しておくとそんな物語だ。
全12話から構成される本作品のなかで、あえて印象的なシーンがあるとすれば、おそらく10人中5,6人くらいは、あの場面を想起するのではないか。
そう、最終話における「こ っ ち み ん な(shita big red)」のシーンである。舞台上ではレヴューがクライマックスを迎えようとしている最中、唐突にキリンがこちらを向き、「あなた」と語り掛けてきたときには、誰もが混乱したはずである。ぼくもした。

なぜ私が見ているだけなのかわからない? わかります。舞台とは、演じる者と観る者が揃って成り立つもの。演者が立ち、観客が望むかぎり続くのです。――そう、あなたが彼女たちを見守り続けてきたように。
一時は混乱したものの、すこし文学や批評をかじったことのある視聴者ならすぐにこう思う――メタフィクションだ!
すこしも文学や批評をかじったことのない人向けにすこし説明すると、メタフィクションとは要は「創作物であることについて自覚的である(構造を持つ)創作物」のことである。あえて広く定義づけたのは、無論「メタフィクション」ということばの取り扱いはいまだ個々人に任されているところがあるし、本論においてはそこを厳密にしておく必要はないと判断したからだ。メタフィクションオタクたちの熱い非難を恐れたわけではけっしてない。
叙述トリックとか、この手のメタフィクションは投じられているだけで狐につままれたような感覚になって、手放しに称揚されることが多い。読者は常に作品に翻弄されたがっているらしい。しかしあらゆる表現技法は手法であってそれ自体は目的ではない。読者や視聴者を翻弄したいだけなら手品でもやっていればいいのだ。問題はその技法が、いかなる効果を生んでいるのかにある。
ここであらかじめ注記しておきたいのは、これから論じていくその効果が、冒頭の古川氏の意図であると証明することが本論の目的ではないということである。創作主体は彼の創作物に対し全能であるというのはとても健気な幻想だ。
つまり本論で考えていくのはあの場面が作品上必要であったかという問題である。勿論(メタ的に言えば)こうしてこの文章が書かれている以上、「必要でなかった」という結論が導き出される可能性の低いことを読者の皆様は予想できるだろうが*1、こうした問題意識のもと考察を進めていくことを確認したところで次に進もう。
<密室>と我々の自意識の所在
<第四の壁>、ということばをご存知だろうか。あるいは<第四隔壁>でもかまわない。
これもまたメタフィクションにすこし明るい読者には聞きなじみのあることばかもしれない。元々は演劇用語で、簡単に言えば舞台上、演者からみて左右後方の3面に加えて、観客と演者を隔てるみえない4つ目の壁のことで、舞台上を一個の独立した<密室>に仕立てるための隔絶のことを指す。それはつまり舞台上の<虚構>と観客の<現実>との境界と換言することができ、現在では演劇だけでなく、フィクション(特にメタフィクション)全般に係る用語として使用される。
諸君が脚本を作るにもせよ、演じるにもせよ、観客はいないものだと思って、それ以上のことを考えてはいけない。舞台の端に諸君を平土間から分つ大きな壁があると考えたまえ。幕が上らなかったの如く演じたまえ。*2
上記に引用したのは18世紀フランスの哲学者、ドゥニ・ディドロ(Denis Diderot)の「演劇論」の一節である。彼の提唱するのはまさしく<第四の壁>概念そのものなのであるが、この意識の目指すところについて、今尾哲也氏は次のように述べる。
個体が自分自身の内部で、自分自身と交す談話を、第三者の存在を意識せずにひそかに告白する場所こそ、<第四の壁>の内なる閉塞的な世界に他ならなかった。*3
つまりこの深い「自己告白の形式」こそ、演者と観客が相互に干渉しあっては成しえないものだと氏は述べるのである。どこまでも閉じた世界のなかで登場人物は現実の我々と同じようにときに煩悶し、ときに歓喜する。そこにあるのは彼ら/彼女らの生活そのものであり、<虚構>として切り離されたはずの物語は、厳然と横たわる<現実>へと変わるのである。
アニメーション作品における<第四の壁>とは、勿論パソコンしかりテレビしかり、その画面、ということになる。『少女☆歌劇レヴュースタァライト』においても、その壁は最終話、キリンが突然画面の外の我々に語り掛け、<第四の壁>の崩壊(あるいは拡張)が起こるまで、十分に機能している。彼女たちの苦悩はみな切実な現実味を伴って我々に迫る。一見してこの壁を破るという行為は、彼女たちの<現実>を陳腐な<虚構>へと陥れる悪手にも見える(というよりこれこそこの手法の難点の全部と言っていい)。とはいえこれが単に無用で、いけ好かないだけの演出であると断定するには早い。作品の傍観者から一転、作品内部へと取り込まれ、密室の住人となること。それが一体何を示すのかに、話を戻そう。
ひとたび<第四の壁>の内側へと引きずり込まれた我々の自意識は、当然物語の開幕当初まで遡及する。我々の作品内部における位置が、この演出により事後的に決定されるのである。ともすればこの作品において<観客>の描写が存在するのが第7話における第99回聖翔祭(おそらく「繰り返し」の起こる以前、つまり初回)にて行われた「スタァライト」のシーンただ一度であることは大変示唆的であろう。華恋とひかりの幼少期の回想シーンですら2人以外の観客は描かれない徹底ぶりである。

要するに、あの空席こそが、我々の自意識の向かう「座」なのだ*4。彼女たちがあくまで「舞台少女」だというのなら、そこには<観客>がいてしかるべきだという至極当然なことに、我々は今更ながら気づくことになる。
安全な物語の<観測者>という立場から<観客>という役に配置された我々に起こるのは、強烈な当事者意識である。我々は当事者として、キリンの悪辣を嫌悪し、またその嫌悪が同属嫌悪であることを悲嘆する。これらの一連の効果は、演劇という構造そのものに担保されている。すなわち演劇という<演者>と<観客>が自然に要請される構造を壁のなかに用意することにより「座」を設けえたという点で、本作は「あなた」の内容を限定せざるを得なかったり、その指示を作品外部へと向けるに至らなかったいくつかの二人称小説などとは一線を画すものとなっているのである。
愛城華恋とは誰だったのか
ところでぼくの「『少女☆歌劇レヴュースタァライト』には一部を除いて<観客>に関する描写が存在しない」という主張に異議を唱えたい読者もいるだろうと思う。なぜなら登場人物(?)のうち、<観客>を自負するキャラクターが1人(?)いるからだ。言わずもがなキリンである。
では本作に登場する<観客>はキリン1匹だけなのだろうか。我々にもたらされた当事者意識は、悪趣味なキリンを嫌悪することの自己矛盾を反射するためだけに機能するのだろうか。我々の無力感には、その先があるのではないか……。
勿体ぶらずに言えば、もう1人、『少女☆歌劇レヴュースタァライト』には<観客>として描かれていた人物がいると、ぼくは考えている。
そう、愛城華恋だ。
愛城華恋は「朝も1人で起きられない」、「主役にならなくてもいい」女の子だ。彼女は今回の「再演」において、神楽ひかりという<装置>がなければ本来「オーディション」の外で物語を終えていたはずの少女である。その特異性については、第9話において大場ななもこう述べている。
でも、どうしてなの? 今回の再演、何が……? ひかりちゃんが参加して始まった、8人のオーディション。再演でいつも最下位だった華恋ちゃんはキャストから外された……。でも! 華恋ちゃんが飛び入りで……! ……ひかりちゃんじゃ、ない? 私の再演を変えたのは、華恋ちゃん……?
愛城華恋は、偶然ひかりのピンチに出くわし、すさまじい決断力と行動力で「オーディション」に飛び入り参加を果たす。もはやこの際2人の過去など棚に放り上げてしまってよい。<観客>だったはずの彼女は<演者>へと転化してみせる。つまり、彼女はありえた我々なのだ。なりえなかった、パラレルな自己を、そこに投影することができる。そして彼女は我々の分身として、物語を終演まで牽引していくのだ。そこにはひとつのカタルシスがあり、またより深い自己内省がある。
我々は愛城華恋になれなかった――この臨場感が、あのキリンの呼び掛けによって成立していることは疑いようがない。
結びに
以上が本論のすべてである。アニメ評論なるものをはじめて書いたものだから、適切な文字数というのがわからず、なんとなくつらつら書いていたら5000字程度になっていた。本当はアニメーション作品の人称や視点の問題にも触れたかったけれど、べつに論旨に関わりがあるかと言われればそんなにない気がしたので省略した。
『少女☆歌劇レヴュースタァライト』はおそらく他にもモチーフの問題(本作には落下や倒れた塔の描写が多数存在する)や「再演」の諸問題など論点が山盛りだ。ぼくはもうしないし、誰かが書いていても読まないだろうけれど、そういうあれこれを考えてみてもおもしろいかもしれない。
オタク、おもしろいアニメを勧めてくれてありがとう。
ぼくは愛城華恋にはなれなかったけれど、ひとまず早起きができるようになることくらいは頑張ろうと思った。



















